人と動物の未来をつくるドッグシェルター
日本全国では約58,907頭の飼い主のいない犬猫が行政のセンターに収容されています(令和3年度環境省)。
キドックスでは、遺棄や虐待に遭った犬を一時保護し、
心身のケアや社会化練習を行うためのシェルターを運営しています。
-
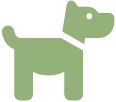
保護犬
-

シェルターで
一時預かり -

譲渡
-

アフター
フォロー

地域に貢献できる
シェルターを目指して
遺棄や虐待に遭った犬猫を一時保護し、心身のケアや社会化練習を行い、新たな里親様へとつなぐアニマルシェルター(動物保護施設)。キドックスは、保護犬が新たな一歩を踏み出せるように一頭一頭向き合うことを大切にしています。
日本や海外にも様々なアニマルシェルターが存在します。
それぞれの団体には方針や特色があり、価値観や大切にしていることも異なります。
そのため、キドックスとしてもシェルター運営における大切にしたい方針や価値観があり、それを具体的にお伝えしておきたいと思います。
保護犬のQOLを大切に考えた施設
※QOL…QualityOfLife(生活の質)
放し飼いや迷子犬や野犬は、外を彷徨い感染症になっている可能性が高く、人との接し方も知らない犬が多いです。キドックスの施設では、そんな犬たちの適切な管理(治療・ケア・トレーニング・日々のお世話等)を行うための、個別犬舎、保護犬専用ドッグラン、空調設備、隔離部屋、トリミングサロンを完備しています。
-

個別犬舎
-

保護犬専用
ドッグラン -

空調設備
-

隔離部屋
-

卒業犬用預かり部屋
-

トリミング
サロン
保護から
里親譲渡までの流れ
STEP1保護
キドックスでは主に茨城県動物指導センターからの保護や、その他関係機関や連携ボランティアさんからの保護を中心に行っています。一般の方からの相談では、人と犬の福祉が侵害される案件については保護対応を行うこともあります。

-
大切にしているレスキュー方針
- シェルターの数とスキルのキャパシティを意識
自分たちが最後まで責任を持てる頭数・状態の犬を適切に判断する - 地域の課題を地域の人と共に解決する
地方移送が当たり前になると地域の課題が隠れてしまい地域の課題解決力を下げてしまうことも念頭に - 悪徳事業者へ加担しない
悪徳事業者の保護下請けになってしまうと悪徳事業者の活動がより活発に - 保護と繁殖引退犬は区分する
繁殖引退犬は事業者が責任を負う必要があるため”保護”という表現は使用せず区分けする - 譲渡困難な犬(噛み犬や老犬など)でシェルターを飽和させない
譲渡困難な犬の割合が一定を超えるとシェルターとしての機能が停滞してしまい、譲渡可能な犬も保護できなくなってしまうリスクを視野に入れておく
- シェルターの数とスキルのキャパシティを意識
STEP2管理
茨城県内では、放し飼いや迷子犬などが多く、寄生虫や皮膚病にかかっている犬が多くいます。そのため心身共に丁寧なケアが必要となり、保護してすぐには譲渡に出すことが難しい子もいます。
保護したらまずは感染症予防のため隔離期間を設けつつ、初期医療(ワクチンや検便や避妊去勢手術等)と健康診断、行動観察などを行っていき、犬の状態を細かく見極めて今後どのようなケアが必要かを判断していきます。また、保護した犬が徐々に人との生活の楽しさを見出せるよう、心身のケアを行いながら、家庭で暮らすための基礎力を育む環境をつくっていきます。

保護したらまずは感染症予防のため隔離期間を設けつつ、初期医療(ワクチンや検便や避妊去勢手術等)と健康診断、行動観察などを行っていき、犬の状態を細かく見極めて今後どのようなケアが必要かを判断していきます。また、保護した犬が徐々に人との生活の楽しさを見出せるよう、心身のケアを行いながら、家庭で暮らすための基礎力を育む環境をつくっていきます。
-
大切にしている管理方針
- 医療や食事や発散はもちろんトレーニングやコミュニケーションも大切にする
- 1頭当たりにかけれる人材とお金と時間を適切に計画する
1頭当たりの人とお金が足りなくなると、犬のQOL低下につながる - 専門家のアドバイザリーに定期的に相談・視察に入ってもらう
シェルターメディスンやドッグトレーニングなど、専門家が介入できる体制にすることで適切な管理体制を維持する
STEP3犬の状態
シェルターの社会的役割は、単なる保護・譲渡という犬の飼育環境の移動だけではなく、シェルターで過ごす間に犬の心と体の状態が良くなることだと考えています。
犬が保護前よりも心身共に良い状態になってから譲渡につなぐことで、適切な犬の飼育の水準(地域の動物福祉の水準)を向上することはもちろん、譲渡の選択肢や可能性も広げることができます。

犬が保護前よりも心身共に良い状態になってから譲渡につなぐことで、適切な犬の飼育の水準(地域の動物福祉の水準)を向上することはもちろん、譲渡の選択肢や可能性も広げることができます。
-
犬の状態の考え方
- 犬の心も身体も保護前より良い状態にすることがシェルターの社会的役割
- 犬の状態を客観的に判断できるように、
キドックス独自の犬の状態の判定システムを導入しています
日・週・3か月など項目によって期間を設定した判定 - 譲渡先の家庭にも譲渡時の犬の状態が客観的にわかる資料を情報提供をしています
STEP4譲渡
保護してから心身の状態が整い、家庭に譲渡できる状態になった保護犬は、里親様の募集を開始します。キドックスでは施設内に保護犬と出会えるカフェを併設し、一般のお客様に保護犬とふれあっていただくことで、里親様を募集するという運営システムです。
カフェ内では、1頭1頭じっくりふれあえるように個室式となっており、「犬生アルバム」という犬の紹介アルバムで犬の性格や個性について理解を深めていただきます。
譲渡型カフェ形式は、譲渡会のように犬に移動の負担をかけることも少なく、毎回場所が変わったり大勢の人に囲まれることが無いため、日常の様子に近い犬の姿を見ていただくことができます。

カフェ内では、1頭1頭じっくりふれあえるように個室式となっており、「犬生アルバム」という犬の紹介アルバムで犬の性格や個性について理解を深めていただきます。
譲渡型カフェ形式は、譲渡会のように犬に移動の負担をかけることも少なく、毎回場所が変わったり大勢の人に囲まれることが無いため、日常の様子に近い犬の姿を見ていただくことができます。
-
大切にしている譲渡方針
- 条件の審査よりも、ご家庭との関係性を大切にした譲渡基準にしています
- お互いに相談できる関係を築くことや、初心者の方には教育的な関わりを重視しています
- 考えが一人の独断に偏らないようにスタッフが3名以上参加する譲渡判定の委員会制度を
設け、犬とご家庭のマッチングを丁寧に時間をかけて検討しています
STEP5アフターフォロー
カフェでのお見合いを経て、トライアル(2週間のお試し飼育)が無事に終了すると、正式に里親様へ譲渡となります。キドックスを卒業した後も、卒業犬と里親様でカフェに遊びに来ていただいたり、ホームカミングデイ(卒業犬の同窓会)を開催して交流したりと、一生のお付き合いが続きます。
メールやお手紙で近況を知らせてくださったり、SNSなどでのやりとりも多いです。
また、犬も人も人生は長いので、家族として共に暮らす過程で、家族の入院、犬の病気、生活面や行動面のことなど、困り事や不安になる事なども出てくることもあり、色々な相談をお受けすることも多いものです。しかし、この「何かあったときに相談できる人がいる」という安心感こそが大切だと考えており、私たちキドックスは里親様に寄り添える存在で居続けたいと思っています。 そのため、譲渡は「終わり」ではなく「始まり」だと考えています。

メールやお手紙で近況を知らせてくださったり、SNSなどでのやりとりも多いです。
また、犬も人も人生は長いので、家族として共に暮らす過程で、家族の入院、犬の病気、生活面や行動面のことなど、困り事や不安になる事なども出てくることもあり、色々な相談をお受けすることも多いものです。しかし、この「何かあったときに相談できる人がいる」という安心感こそが大切だと考えており、私たちキドックスは里親様に寄り添える存在で居続けたいと思っています。 そのため、譲渡は「終わり」ではなく「始まり」だと考えています。
-
譲渡後に大切にしていること
- 譲渡後もお互いにコミュニケーションをとりたくなる関係をつくる
定期的な報告を強制する関係ではなく、関係を続けたいと思ってもらえるように - 困りごとの相談だけでなく、楽しい嬉しい近況報告など、
親戚のおじちゃんおばちゃんのような存在を目指しています - 譲渡後も犬とご家族の生活に伴走できるように、
ニーズに沿った仕組みやサービスをつくっていく
- 譲渡後もお互いにコミュニケーションをとりたくなる関係をつくる
STEP6社会への影響
上記の活動を1つ1つ丁寧に継続していくことで、犬と人、人と人との良い関係性が地域社会に増えていくと信じています。社会課題に対する世間の声が大きくなるにつれて、仮に規則や罰則が多くなると、犬と暮らす人口自体が減り、人と犬の関係そのものが減ってしまいます。
動物の恩恵を受けた人が減ると、動物福祉の担い手も減ります。また、保護という名目を利用したビジネスが増加することで、動物福祉が侵害されている実情もあります。当会の動物保護施設(アニマルシェルター)が、動物にも人間にも良い福祉的モデルとなるようにこれからも活動に真摯に取り組んでいきます。

動物の恩恵を受けた人が減ると、動物福祉の担い手も減ります。また、保護という名目を利用したビジネスが増加することで、動物福祉が侵害されている実情もあります。当会は、人と犬の良い関係や動物の恩恵を受けた人が地域に増える活動を目指すことで、長期的に人と動物の福祉の土壌を育み、動物保護施設(アニマルシェルター)の存在が動物にも人間にも良い福祉的モデルとなるようにこれからも活動に真摯に取り組んでいきます。
犬に関するご相談
犬に関するご相談をご検討の方は
必ずご確認ください
まずは該当する相談内容をご確認いただき、必要に応じて、茨城県動物指導センター・市町村役場・最寄りの警察署にもご相談になってから、当会までご相談ください。
各機関への相談経過後のほうが、その後の対応についてアドバイスをしやすいため、お手数ですがご協力をお願いいたします。
-
動物を拾った・保護して欲しい
犬を拾ったときの
保護から譲渡までの流れ-
首輪・リード・迷子札・鑑札等を確認する
まずは飼い主さんの連絡先がどこかに書いてないか確認してください。 -
茨城県動物指導センター、市町村役場、最寄りの警察署に連絡する
その際に、拾った動物の詳細情報を聞かれるので答えられるようにしておきましょう。探している飼い主さんがいるかもしれません。 -
動物病院へ連れていき、マイクロチップの有無を確認する
マイクロチップは動物指導センターでも確認してもらえます。マイクロチップが入っていた場合は、マイクロチップ登録機関に問い合わせて飼い主を照合します。 -
動物病院にて健康診断を行う
検便、感染症などの病気の有無、ワクチン接種などの基礎医療を行ってもらいます。- ご自宅に先住犬猫がいる場合は、感染症予防のために2週間程度隔離して様子を見ましょう。ご自宅で隔離できる世話部屋などを用意するか、難しい場合は動物病院へ入院をを相談してみましょう。また、双方が避妊去勢をしていない場合は、2週間隔離完了後も隔離してお世話する必要があります。
-
トリミングサロンでシャンプーをする
汚れの程度によってはトリミングサロンでシャンプーしてもらいましょう。 -
遺失物期間3ヵ月※1が経過したら、里親を探す
譲渡会への参加や、インターネットの里親募集サイトやSNSなどを活用して募集しましょう。
※1 保護した犬猫は、3ヵ月間は遺失物扱いになります。警察署に遺失物として届け出ると、掲示板に迷い犬保護が公告されます。公告後3か月経過して遺失物の持ち主が判明しなかったときには拾得者が所有権を取得します。そのため、警察署に届出後3ヵ月間の遺失物期間は他者に譲渡できません。
困った時は
保護する場所がない、お世話ができない、動物病院代が払えない…など、ご自身では保護が不可能と判断したら、保護する前にまずは茨城県動物指導センター(0296-72-1200)に相談してみしましょう。
それでも解決が難しい場合は、以下のフォームから当会へご相談ください。 -
-
飼っている動物を手放したい・引き取って欲しいときはどのようにしたら良いですか?
-
茨城県動物指導センターに相談する
-
保護団体に相談する
茨城県動物指導センターに登録している登録団体は茨城県内を対象に保護活動をしています。お住いの最寄りの保護団体に相談してみましょう。その際に、保護団体によって専門性(犬・猫・犬種・小型・大型・エキゾチック専門など)がありますので、その点にも留意したうえで相談するようにしましょう。
-
里親を探す
一時的に預かってくれる方がいる場合は、まずは預かってもらいながら、里親を募集していきましょう。譲渡会への参加や、インターネットの里親募集サイトやSNSなどを活用して募集しましょう。
-
-
飼っている動物が迷子になったときどのようにしたら良いですか?
-
心当たりのある散歩コースなどを徹底的に探す
初動が何より重要です。いなくなってから数時間はまだ近くにいる可能性が大きいため、まずは心当たりのある散歩コースなどを徹底的に探しましょう。 -
茨城県動物指導センター、市町村役場、最寄りの警察署に連絡する
犬が迷子になった旨を伝えましょう。 -
庭や玄関先などに捕獲機や餌や監視カメラなどを設置する
性格などを踏まえて、自宅に戻ってくる可能性がある子の場合は、庭や玄関先などに捕獲機や餌や監視カメラなどを設置しておきます。 -
目撃情報を集める
- カラーのチラシ作成、印刷
- チラシ配り(電柱やお店への貼りだし、通行人への聞き込み等)、ポスティング
- SNSでの拡散、場合によっては専用アカウント作成
-
動物指導センターの公示情報を毎日チェックする
-
新聞折込を手配する
3日経っても目撃情報がない場合は、広範囲にわたっての目撃情報の収集が必要なため、新聞折込の手配を行いましょう。 -
捕獲する
目撃情報によって場所が特定できてからは、捕獲機の手配・設置・監視カメラの設置・張り込み・餌の取り替えなどを捕獲できるまで行います -
無事に保護できたら、きちんとチラシの回収やお礼回りを行う
-
-
動物虐待を見つけたのですが。
-
虐待の証拠や記録を出来る限り集める
虐待の動画や写真、録音など、虐待であると第三者が客観的に判断できる証拠をできる限り集めます。
近所の人の証言や目撃情報なども集めましょう。いつ、どこで、だれが、何と証言したのか記録もきちんととっておきます。 -
茨城県動物指導センター、市町村役場、最寄りの警察署に連絡する
その際に、事前に集めておいた具体的な情報や証拠が必要になります。
虐待加害者との関係性によっては匿名での通報も可能です。 -
協力者を探す
虐待の証拠集めから通報までを一人で全て対応するのは身も心も大変なことです。
一緒に協力して進めてくれる方(家族、友人、ご近所の方など)や、動物愛護団体などに協力を仰ぐことも大切です。 -
ケースによっては専門家を頼る
今後の進め方について動物愛護法に詳しい弁護士に相談したり、証拠集めを探偵に依頼するなど、困り事に応じて適宜専門家に相談することも視野に入れておきましょう。
動物虐待は禁止されています(環境省HPより)
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金 - 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金 - 愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物とは
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
-







